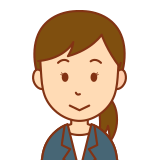
こんにちは!
「すてきな保育士の仕事」を運営しておりますHIROKOです。
私は保育士として、区立・私立の認可保育園での勤務経験を持ち、認可外保育園を7年間運営者しておりました。
現在は子育てをしながら保育士の相談を受けたり、サイトの運営をしています。
保育士に憧れてせっかく取った資格を、悩みで無駄にしない為に、今いる環境を変えてみるのも一つです。
すぐに転職を考えない場合でも、転職サイトのコンサルタントへ相談することで今の立ち位置を知る事ができます!
3歳児以下の調理計画の事例・書き方、見本です。
保育園の規模やクラスの子どもの状況、地域などによっても変わってくると思いますので、自園・クラスにはどのような形が合うか一緒に考えてみましょう。
調理目標
◯子どもたちの成長に合わせ、一日の活動と成長に必要な栄養素をバランスよく取り入れ、安全でおいしい給食を提供する。
◯旬の食材を取り入れ季節感を出したり行事食を取り入れたりと、献立にも工夫を凝らす。
また不足しがちな野菜や魚を献立に多く取り入れる。
◯手作りを基本とし、食品の持ち味を生かすために薄味にする。
だしは昆布・煮干しなどとし化学調味料は使用しない。
合成保存料や着色料など、添加物の含まれている食品は使用しない。
衛生
食品衛生の基本、5S(整理・整頓・清潔・清潔・習慣)を毎日実行。記録をつけ毎日漏れがないように実行する。
アレルギー対応
食物アレルギー対応を行う園児の情報共有、調理器具・食材の管理、調理担当者の区別化、調理作業の区別化、確認作業の方法、確認作業の方法・タイミング、調理場における対応の評価を徹底する。
様子
離乳食初期 (5~6ヶ月)
機嫌の良い日を見計らってスタートする。
ドロドロ・ポタージュ状の食品を上手に飲み込めるようになる。
離乳食中期 (7~8ヶ月)
離乳食開始から2カ月ほどたち、2回食にも慣れ唇を閉じてゴックンと飲み込むことができるようになる。
離乳食後期 (9~11ヶ月)
やわらかくした食べ物を舌でつぶして食べられるようになる。
離乳食完了期(12~1歳)
乳幼児食を食べやすく配慮した食事を食べる。
幼児食(1歳~2歳)
スプーンやフォークを上手に使えない子どもや手づかみの子ども等、個人差があるが幼児食を食べられるようになる。
様子からの今後の対応
離乳食初期 (5~6ヶ月)
少しずつ水分を減らしてジャム状のものを飲み込む練習をする。無理なく進める。
離乳食中期 (7~8ヶ月)
唇を閉じてゴックンと飲み込むことができるようになったら、舌でつぶせる固さの食事へとステップアップしていく。
離乳食後期 (9~11ヶ月)
歯ぐきでを押しつぶせる固さにチャレンジするカミカミ期にステップアップしていく。食事回数も3回に増やしていく。
離乳食完了期(12~1歳)
一口大の肉などは、歯ぐきでかみつぶせないので、ひき肉団子などで対応する。
野菜などは軟らかく煮てから提供する。かみ切りにくい、こんにゃくやごぼうなどは除く。
幼児食(1歳~2歳)
濃い味を好み始めるが薄味を心掛ける。個人差があるので刻み等配慮する。
食材
離乳食初期 (5~6ヶ月)
・つぶしがゆ・人参・かぼちゃ・じゃがいも・さつまいも・キャベツ・かぶ・トマト・いちご・メロン・バナナ
離乳食中期 (7~8ヶ月)
穀類(7倍がゆ等)+たんぱく質+汁物味付けは、塩・醤油・味噌・ケチャップ・砂糖等(素材の味を生かす程度)
離乳食後期 (9~11ヶ月)
穀類(軟飯)+たんぱく質・野菜+汁物
○歯ぐきで押しつぶせる固さ(バナナ位)
○薄味を心掛ける(大人の1/4位の味付け)
離乳食完了期(12~1歳)
多くの食材を経験することが、味覚の形成につなげる。
幼児食(1歳~2歳)
多くの食材を経験することが、味覚の形成につなげる。
調理方法
離乳食初期 (5~6ヶ月)
調味料を使わずに、素材そのものの味を知らせていく。くせのない野菜を使う。
やわらかく煮てすりつぶした後、スープを加えポタージュ状にする。
4週目からタンパク質を加える。水溶き片栗粉でとろみをつける。
離乳食中期 (7~8ヶ月)
やわらかく煮て、荒つぶしにする。食材は豆腐くらいの舌でつぶせる固さ。
汁物は出し汁か野菜スープで煮て、調味料で味付けする。
離乳食後期 (9~11ヶ月)
・食パン(そのままか)またはトーストする)
・豆腐ステーキ
・人参の煮物・茹でブロッコリー
★この時期は小さく刻みすぎると飲み込み食べになりがちなので、柔らかく煮たものをある程度の大きさに切るか手で持ちやすいように切る。
離乳食完了期(12~1歳)
薄味を心がける。
濃い味付けは、後に生活習慣病の引き金になることもあるので、素材の味を生かした料理で、「おいしい」と感じる力を育てる。
幼児食(1歳~2歳)
薄味を心がける。濃い味付けは、後に生活習慣病の引き金になることもあるので、素材の味を生かした料理で、「おいしい」と感じる力を育てる。


